
アパート経営を始めると、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。
これまで、社会に出てからずっと企業勤めで、確定申告をしたことがないという方もいるでしょう。今回は、確定申告1年目の方に向けたポイントなどを紹介します。
収入と所得の違いを押さえよう
確定申告の作業に移る前に、まずは納税の仕組みについて簡単におさらいしましょう。そのためにはまず、収入と所得の違いを押さえておくことが大切です。
収入とは、企業でいえば売上高のことです。不動産経営でいえば家賃、共益費、礼金、敷金、保証金、更新料などのうち、返還する必要がないものをいいます。なお、太陽光発電による売電収入がある場合はそれも含みます。
一方で、所得とは「収入から必要経費を差し引いたもの」のことを指します。「手取り」や「利益」と考えるとわかりやすいでしょう。
所得は税務上10種類に分類されており、不動産所得のほか、給与所得などすべての所得を合計した額が課税対象となります。
青色申告と白色申告の違いを押さえよう
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。以前は、白色申告には記帳の義務づけがありませんでしたが、2014年からはどちらも領収書の保存と記帳が義務づけられています。
なお、青色申告の場合、10万円控除と65万円控除という2種類の控除があります。当然ながら65万円控除の方がお得ですが、この控除を受けるには、所有不動産が「5棟10室」という事業的規模が必要となります。
青色申告の場合、仕事を手伝ってくれた家族への給与を経費として計上できる「専従者給与」が経費として認められ、控除の対象となります。
一方、サラリーマン大家でアパートを1室だけ貸しているような場合は、白色申告か青色申告か迷うかもしれません。青色申告だと若干、申告書の作成に手間がかかるので「白色でいいや」と思う方もいるかもしれません。しかし、白色申告には、青色申告で受けられるさまざまな節税メリットがありません。
所有不動産の規模が小さくても10万円の控除は受けられるので、青色か白色で迷ったら青色申告を選びましょう。
経費の内訳を押さえよう
不動産収入のうち、経費として計上できるものには「租税公課」「損害保険料」「委託管理費」「修繕費」「減価償却費」「借入金利子」「手数料」「弁護士や税理士報酬などの外注費」などがあります。
租税公課とはこの場合「固定資産税」「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」「事業税」などが含まれます。また、ローンの返済額のうち利息相当分や、物件管理のための交通費なども経費になります。
このうち、注意しておきたいのが修繕費と減価償却費です。入居者の退去に伴う内装工事や、設備機器の入れ替え費用は修繕費として計上できます。一方で、建物の資産価値を高めるための修繕は、減価償却費として、決められた年数でかかった費用を分割して計上しなくてはいけません。減価償却費の計算は、会計ソフトを使うと簡単にできます。
経費として計上できないものには、ローン返済額のうち元本に相当する部分、賃貸住宅と自宅が兼用になっている場合の自宅の光熱費や損害保険料などがあります。自宅分と賃貸住宅分の費用は、建物面積か使用割合に基づいて按分します。
確定申告は税理士に依頼できる?
もし、本業が忙しくて申告書を作成している時間がないという場合は、税理士に依頼することも可能です。税理士に依頼した場合の相場はだいたい5万~10万円で、報酬は経費として計上できます。ただ、すべてを税理士に丸投げにしてしまうと、自分の所有不動産の収支が分からなくなってしまい、これでは投資家失格です。
忙しくても1年のおおまかな収支は把握しつつ、それを税理士に依頼してまとめてもらうというやり方がいいでしょう。
確定申告は一度慣れてしまえばそれほど難しくはないので、申告書作成のノウハウを身につけてしまうのも一つの手です。
【オススメ記事】
・アパート経営でトクする土地活用 知っておきたいメリット4つ
・初心者必見、はじめての賃貸経営で気をつける4つのポイントとは
・アパート経営で低い空室率を維持するための秘訣とは?
・賃貸経営の節税に対して知っておきたい3つの方法
・実は保険効果と年金効果がある!! 賃貸経営の本当の魅力とは
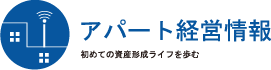 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


