
世の中は日々変化しています。また、アパートやその経営環境も刻々と変わっていきます。そうした中で、アパートを手放したり建替えたりすることが望ましい時期が必ず訪れるといえます。アパート経営に失敗しないためには、投資時点から売却や建て替えを想定して経営することが重要でしょう。
着眼点1:躯体の寿命
アパートは、建てたその日から物理的な劣化が始まります。劣化を少しでも食い止めるために、日常的なメンテナンスや大型修繕を行いますが、それでも居住困難になる日がいつか訪れます。
地震大国の日本では、ヨーロッパのように石造りの構造物を建築する余地が小さいこともあり、大半の建物は数十年で寿命が尽きます。奈良県の法隆寺のような長寿命の木造建築物もありますが、こうした国宝と違い一般的な建物には多額の修繕費用をかけられないため、直すより建て替えた方が安いと判断すれば取り壊すことになります。
構造材、工法、塩害の有無などの立地環境、メンテナンス状況などによりますが、短くて30年、長くて70年程度で建て替え時期を迎えるアパートが多いのではないでしょうか。
建て替え費用の工面が困難と考えられる場合は、躯体の寿命を見越して早めに売却することが重要ともいえます。
着眼点2:居住空間の寿命
躯体寿命より早く居住空間の寿命が到来することもあります。要するに「時代遅れの部屋」になってしまうということです。
その典型例が1950年代から70年代にかけて日本住宅公団(現都市再生機構:UR)が建築した大規模団地です。鉄筋コンクリート造の団地は、日常のメンテナンスと大規模修繕を計画的に行っていれば、まだ住み続けられるはずです。
しかし、専有面積と比べ間数が多い、和室が多い、天井が低いといった住戸の造りやエレベーターが敷設されていないことがネックとなり、人気が低下しています。そのため、多くの居住可能団地が建て替えられました。
アパートも1970年代頃までは、「風呂なし、トイレ・玄関共同」が当たり前でしたが、今ではシェアハウスを除きそうした新築物件はまず見当たりません(シェアハウスでも共同風呂はあります)。
こうした簡素な造りの築40年程度のアパートは、躯体の堅牢性は十分保っていても、使い勝手の悪さから敬遠されてしまいます。家賃を大幅に下げても赤字にならなければ経営を維持できますが、そうでなければ売却か建て替えを避けて通れなくなります。
着眼点3:街の寿命
人や建物だけでなく街にも寿命があります。長崎県の通称「軍艦島」はかつて炭鉱の島として栄えましたが、今は無人の廃墟島になっています。これほど極端でなくても、地場産業の衰退や大学の移転などにより人口が大幅に減り、活気が失われた街は少なくありません。
アパート経営に失敗しないためには、街も人と同じように成長、安定、衰退、(消滅)というサイクルを辿る可能性があることを認識して、物件の売却時期を見極めることが重要です。
例えば、郊外の学生向けアパートであれば、地元大学の受験者数や偏差値の推移、卒業生の就職実績などを継続的に把握し、移転や規模縮小の可能性を予測したうえで早めに売却することが望まれます。
交通の利便性が高ければ、一旦衰退した街が再生されることもあります。東京都心5区などでは、そうした事情を踏まえ、古いアパートの所有を続ける戦略も考えられます。
物事の成功の可否は、「上手く終わらせること」にかかっています。多額の財産を築いた人でも、不遇な晩年を過ごせば成功した人生とはいいがたいでしょう。一方で、若い頃から苦労が絶えなくても健康に長寿を全うした人は、周囲から幸せな人生だったと思われることでしょう。アパート経営でも、売却や建て替えが成功のカギとなります。
【失敗しないコツ】シリーズ
・アパート経営で失敗しないコツ #1(アパートとマンションの違い編)
・アパート経営で失敗しないコツ #2(物件編)
・アパート経営で失敗しないコツ #3(立地・環境編)
・アパート経営で失敗しないコツ #4(資金調達編)
・アパート経営で失敗しないコツ #5(家賃編)
・アパート経営で失敗しないコツ #6(管理編)
・アパート経営で失敗しないコツ #7(災害編)
・アパート経営で失敗しないコツ #9(総括編〜資産形成に向けて〜)
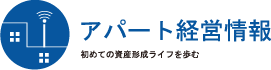 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


