
投資を行う場合、いろいろな経費がかかります。たとえば、株式投資には、購入金額の約1%以下の購入手数料がかかります。また、投資信託への投資には、購入金額の約3%以下の購入手数料や預け入れ金額の年間約2%以下の信託報酬(管理運用費)がかかることが一般的であり、購入する証券会社や銀行、また各商品によって購入手数料が異なることや、ゼロになるケースもあります。
金融商品の場合、かかる経費は上記の種類で済むことがほとんどですが、不動産のような実物資産への投資には、さまざまな費用が発生します。さらにその金額は、かなりまとまった金額になります。想定外とならないよう、事前にしっかりと資金計画に組み込んでいく必要があります。
アパート経営にかかる経費とは
まず、アパート経営にかかる経費を所有前にかかる初期費用と、所有後にかかる運営経費に分けて見ていきましょう。
●初期費用
1. 登記費用
保存登記、移転登記、抵当権設定登記など法務局に登録する場合、登録免許税が必要です。土地と建物それぞれの固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算します。約30万~60万円かかります。また司法書士報酬は、その内容によって異なります。
2. 仲介手数料
不動産物件を探し、売り主との交渉をしてくれる不動産業者に支払う報酬です。
物件の3%+6万円がかかります。
3. 印紙代
売買契約書に貼る印紙代です。物件が5,000万円ちょうどの場合、1万円です。
4. 火災保険10年一括
オーナーが入る火災保険は、「建物」を補償する保険です。さらに建物の老朽化により、水漏れが発生し、入居者の家財にダメージを与えた場合は、オーナーが損害賠償責任を負うことになります。そのために火災保険に特約として「施設賠償責任」保険に入るのが有効です。地震保険を付けて約30万~50万円です。
5. 融資手数料と印紙税
物件購入時には、融資を受けるケースが多いと思います。金融機関にもよりますが、融資金額の1~1.5%が手数料として取られることが多いです。さらに借り入れを行う場合、必ず金融機関と金銭消費貸借を締結します。その場合、印紙税がかかります。
6. 不動産取得税
土地や建物を取得したときにかかる税金です。取得後半年から1年経って、自治体から納税通知がきます。土地と建物の固定資産税評価額に3%または4%の税率をかけて計算されます。
ここまで物件取得時にかかる諸経費を見てきましたが、おおよそ取得価格の5~8%程度を見込むとよいでしょう。
●運営経費
1. 修繕費(修繕積立金)
物件の経年劣化は避けられません。さらに、大規模修繕となると大きな金額となりますので、計画的に修繕費用を積み立てる必要があります。建物の築年数によって変わりますが、目安として賃料の3~5%程度を積み立てることが必要といわれています。
2. アパート管理費用
アパート経営における家賃収受業務など、入居者管理や清掃業務などを専門業者に任せる場合、管理会社へ報酬を支払う必要があります。その場合、家賃の8~10%程度が相場です。
3. 固定資産税・都市計画税
収益物件を所有していると、固定資産税や都市計画税がかかります。税金の支払先は、物件所在地の市区町村です。固定資産税の計算は、固定資産税評価額から課税標準額を出し、それに通常1.4%をかけて算出します。都市計画税は、課税標準額に最高0.3%をかけた金額です。
アパート経営で節税できる3つの税金、節税例
アパート経営によって節税できる可能性があるのは、所得税、住民税、相続税です。
1. 所得税
アパート経営によって得られる所得は、不動産所得です。もし、これ以外の所得、例えば給与所得などがあれば、それと損益通算して申告します。もし、不動産所得が赤字であれば、合計所得が少なくなり、納める税金も少なくなります。不動産所得の算出方法は、収入から各種経費を差し引いた金額です。経費に落とせるものが多ければ赤字になり、他の所得と合わせることで節税になります。
2. 住民税
住民税は、所得税を元に計算しますので所得税が節税できれば住民税も節税できます。
3. 相続税
相続税を計算する場合、土地建物などの不動産の評価額は現預金と違い、土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額で計算します。土地ならびに建物の相続税評価はともに、時価に比べて7~8割の評価になるケースが多く、現預金を不動産に変えておくことで相続税を抑える効果を期待できます。
以上のように、アパート経営を行う際に諸経費をしっかりと見積もることが、不動産投資の成功の大きな要素です。
これらの経費をきちんと物件利回りに反映させて、実際に残る金額を算出し、キャッシュフローを把握することの大切さがお分かりいただけたのではないでしょうか。
【おすすめ記事】
・これで完璧! 不動産投資の節税対策
・サラリーマン大家の年収は?始めるなら頭金は?
・賃貸経営の節税に対して知っておきたい3つの方法
・実は保険効果と年金効果がある!! 賃貸経営の本当の魅力とは
・サラリーマンや公務員こそアパート経営を始めるべき理由
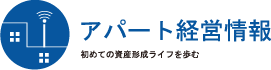 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


