
日本は四季の変化に富むとともに四方を囲む海、奥深く急峻な山、豊富な水量をたたえる川など多彩な自然環境に恵まれた国です。それらの環境は農業、漁業、観光業などの発展に大きく貢献する一方で、さまざまな災害をもたらす原因にもなっています。アパート経営に失敗しないためには、こうした災害に対する多面的な対策が求められます。
災害対策1:ハザードマップのチェック
全国の市町村では災害による被害予測を示したハザードマップの作成・公表を行っており、「国土交通省ハザードマップポータルサイト」で各自治体の整備状況を確認できます。
ハザードマップにはさまざまな種類があります。上記の国土交通省サイトでは洪水、内水、高潮、津波、高潮、土砂災害の5種類を掲げていますが、そのほかには地震のハザードマップを作成している例が多くみられます。
地震ハザードマップには、地盤の強度だけでなく、木造住宅密集地や高層ビル街などの現存する建築物の状況を踏まえた倒壊リスクや火災(延焼)リスクを表示したものもあります。
各自治体とも沿岸部、山間部、内陸部など地域特性からみてリスクが高いと想定される災害のハザードマップを作成しています。これらは各自治体のウェブサイトに掲載されているほか、庁舎で詳細な資料を閲覧することもできます。
池、沼、沢、谷など水を想起させる名前の町は、埋立地で軟弱な地盤の可能性があります。同様に台、丘などがつく町名は丘陵を切り崩した造成地で、土砂災害のリスクが高いかもしれません。こうした点も踏まえ、ハザードマップをチェックすることがとても大切です。
災害対策2:建物修繕・設備増強
建築技術は日進月歩で向上しています。耐震、免振、制振などの地震対策は、日を追うごとに進んでいます。塗料や建材の耐火・防水性能も着実に改善されています。
このような技術革新や建築基準法、消防法などの法令改正の可能性を予め織り込みながら長期修繕計画を策定したうえで、的確に修繕・補強を進めることが重要です。とくに1981年(昭和56年)の建築基準法改正以前に建築確認を受けた建物の場合は、耐震性能が大きく劣っている可能性があるため十分な検討が必要です。
防災設備の整備も重要です。消防法に基づく消火器・消火栓などの設置に加え、浸水・津波被害が予想される地域では救命胴衣や避難用ボートなどを備え付けることも考えられます。こうした避難用具や設備はアパートの保全に直接結び付きませんが、物件の付加価値を高めるうえでは効果的です。
災害対策3:損害保険の加入
どんなに準備しても災害による被害を完璧に防ぐことはできません。近隣の失火による延焼、地震による建物の倒壊・損傷、台風や洪水・津波による浸水・流失などの被害は一定の確率で発生することを認識すべきです。そのうえで保有アパートの立地分散を図るとともに、損害保険に加入して実質的な被害を縮減することが大切です。
火災保険だけでなく地震保険にも加入することが重要です。火災保険は地震による火災には適用されません。一方で、地震保険は地震に起因する建物の倒壊・損壊、火災などに対応しています。津波や噴火による被害も補償対象になります。入居者にも火災保険への加入を求め、自らが起こした火災の損害賠償請求へ応じられるよう準備してもらうことも欠かせません。
災害にはリスクが顕現化した際のインパクト(被害額)は大きい一方、その発生頻度は低いという特徴があります。そのため潜在的な危機意識は持っているものの、平穏な日常生活が続く中で対策を怠っている人が多くみられます。
アパート経営に失敗しないためには、こうした多数派の根拠のない安心感に染まることなく「いつか必ず発生する災害」に対する備えを怠らないことが大切であるといえるでしょう。
【失敗しないコツ】シリーズ
・アパート経営で失敗しないコツ #1(アパートとマンションの違い編)
・アパート経営で失敗しないコツ #2(物件編)
・アパート経営で失敗しないコツ #3(立地・環境編)
・アパート経営で失敗しないコツ #4(資金調達編)
・アパート経営で失敗しないコツ #5(家賃編)
・アパート経営で失敗しないコツ #6(管理編)
・アパート経営で失敗しないコツ #8(売却・建て替え編)
・アパート経営で失敗しないコツ #9(総括編〜資産形成に向けて〜)
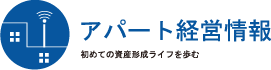 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


