
アパート経営に失敗しないためには、資金調達計画を的確に策定することが大切です。慎重な人は可能な限り借入金額を減らすことが望ましいと考えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。自らのリスクテイク力と目標ポートフォリオ次第で望ましい借入金比率は異なります。
リスクテイク力の把握
まず、自分がアパート経営に失敗した場合のダメージを想定しましょう。経営に行き詰まれば次善策として物件を処分することになります。その場合、ローン残額をすべて返済できない可能性が高いと考えられます。
したがって、他の収入や資産で残債を返済できる資金調達計画を立てる必要があります。銀行預金を最大で1,500万円取り崩せる、元本1,000万円の借入金を10年で返済できる収入があるなど、アパート経営に失敗しても負債を返済できる範囲(リスクテイク力)を認識することが大切です。
リスクテイク力を判断する際には、金利上昇の影響を検討することも重要です。金融機関は長期貸出の金利固定化を避けたい(金利リスクを減らしたい)と考えています。このため固定金利ローンを選択すると相対的に高い金利になりがちです。
一方で変動金利型ローンの場合は、金利上昇時に家賃相場や地価が十分に上がらなければ赤字経営に陥るリスクがあります。
目標ポートフォリオの設定
中長期的な目標ポートフォリオによっても資金調達計画は変わります。例えば1億円の自己資金のある人が銀行預金よりも少し高い運用利回りを確保できれば十分と考えていれば、100%自己資金で人気の高い場所にアパート1棟を建てれば十分でしょう。
一方で本格的なアパート経営に乗り出すことを考えているのであれば、可能な限りローンを組んで1億円の自己資金を多くの物件に分散することを検討すべきです。
利回りの低い(収益の安定性の高い)物件から徐々に投資を始めれば、失敗するリスクも小さくなります。万が一、経営に失敗して物件を処分することになっても、手元に資金を残しておけば残債を返済しやすくなります。
借入金融機関の選定
一般的にアパート経営に必要な初期投資額の大半は、金融機関借入により調達します。
金融機関の探し方は2つに大別されます。1つは、自分で金融機関を探す方法です。もう1つは、アパートの建設販売を手掛ける不動産会社に紹介してもらう方法です。
前者の場合、都市銀行、地方銀行、信用金庫など幅広い金融機関に対し自由に借入申込みを行えます。ただし、自分で土地の取得・建設計画、入居者の募集方法、開業後の収支計画などの資料を整理して説明しなければなりません。また第三者保証(信用保証協会、民間保証会社など)の利用や団体信用保険の加入などに関し、より厳しい条件を求められる可能性もあります。
一方、後者であれば借入可能な金融機関はある程度絞られますが、不動産会社と金融機関の間の事務手続きが標準化されており資料提供や説明をより円滑に進められます。また紹介不動産会社が過去に手掛けたアパートの入居率、売上高利益率、借入金延滞率などの経営指標がアパート市場全体の平均より優れていれば、一段と有利な条件で調達できます。
「頭金0円」、「100%ローン」、「融資期間35年」でアパート経営を始めることも夢ではありません。
アパート経営に失敗しないためには、資金調達、土地探し、建設、入居者募集、施設管理、入居者対応などの業務をすべて自分が統括する場合と、アパート建設販売の専門業者をパートナーにする方法の何れがよいか見極めることが大切です。
一般的には信頼できる専門業者を見極めて、そのノウハウやコスト削減力を活用する方が低リスクで安定的な収益を確保できると考えられます。「餅は餅屋に任せる」ことが、アパート経営に失敗しないための秘訣かもしれません。
【失敗しないコツ】シリーズ
・アパート経営で失敗しないコツ #1(アパートとマンションの違い編)
・アパート経営で失敗しないコツ #2(物件編)
・アパート経営で失敗しないコツ #3(立地・環境編)
・アパート経営で失敗しないコツ #5(家賃編)
・アパート経営で失敗しないコツ #6(管理編)
・アパート経営で失敗しないコツ #7(災害編)
・アパート経営で失敗しないコツ #8(売却・建て替え編)
・アパート経営で失敗しないコツ #9(総括編〜資産形成に向けて〜)
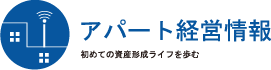 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


