
住宅を選択する際には、誰でも必ず利便性や周辺環境を考慮します。どんなに立派な建物でも、山奥の崖下の家には、特別な目的がない限り住みたいと思う人はいないでしょう。アパート経営で失敗しないためには、よい立地の物件を割安で仕入れる目利き力が重要になります。
交通の利便性
立地で最初に検討されることは交通の利便性です。ほとんどの人は、通勤・通学時間を基に居住可能圏を設定してから物件を探します。このため当然ながら多くの人にとって通勤・通学圏となる地域は人気が出ます。
東京、大阪、名古屋などの大都市圏では電車通勤・通学者が多いため、駅チカ物件が好まれます。その中でも都心まで数十分かかる郊外では、多くの人がより利便性の高い急行・快速停車駅、複数路線発着駅の近くで物件を探します。
各駅停車しか止まらない駅の場合は、急行・快速停車駅の1つ先(郊外寄り)の駅が狙い目です。なぜなら、隣の駅で急行・快速に乗り換えられるからです。
また朝のラッシュ時に座って通勤・通学できる始発駅も人気があります。東京圏では、中央線・武蔵小金井駅、京浜東北線・南浦和駅など、急行・快速が停車しない駅が穴場です。
車社会の地方都市では、幹線道路に近い立地が好まれます。また中心部への距離よりも、渋滞に巻き込まれず中心部に出られることが重視されます。
生活の利便性
スーパー、コンビニ、量販店、飲食店、娯楽・文化施設、医療施設、教育機関からの距離も、重要な評価要素です。大都市圏では駅前に商店街が広がっている場所が多いため、基本的に「駅チカ=利便性が高い」と考えられます。
ただしマイカー保有率の高い郊外では、駅から多少遠くても数キロ圏内の生活関連施設が充実している場所も人気があります。とくに専業主婦や小学生以下の子どもは電車に乗る機会が限られるため、広くて使い勝手のよいファミリー向け物件には一定の需要があります。
地方都市では、大型ショッピングモールに近い場所が人気です。生活の利便性という観点では、中心部やターミナル駅からの距離はあまり重視されないでしょう。
環境の快適性
治安の良し悪しも物件選択の重要な材料となります。下町や繁華街・工業地帯の治安を心配する人は少なくありません。
治安とともに騒音も物件の人気を左右します。駅前や幹線道路沿いは利便性が高い一方、騒音が懸念されます。ただし鉄道や幹線道路の近くでも、遮音効果を果たす大きなビルの後ろに建つ物件では、あまり騒音が気になりません。
逆に駅から少し離れた住宅地では、静かすぎて治安の心配をする人もいます。「閑静な住宅街」が必ず好まれるわけではないようです。
学校やスポーツ・娯楽施設の近くも時間は限られますが、一定の騒音が発生するため敬遠されがちです。競馬場、競輪場など公営ギャンブル施設に近いエリアも同様のことがいえるでしょう。
マイナスをプラスに、戦略を考える
しかし、このようなマイナス要素を逆手に取り土地を安く仕入れた上で、それらを気にしない人たちを意識した物件戦略も考えられます。学校の隣でファミリー向け、競馬場の近くで独身男性向けのアパートを建てることも一案です。
アパート経営に失敗しないためには、誰もが一等地と考える場所に物件を建てるのではなく、多少マイナス要素がある立地でハンディを逆手に取ったり建物に付加価値をつけたりして入居者を集めることを考えるべきです。
人気の立地では、築古アパートを安く買い取りリノベーションをして、付加価値を高める戦略が有効でしょう。誰もが住みたがる場所で新規に土地を取得してアパートを建てても、赤字になって失敗するリスクがあることを肝に銘じてください。
【失敗しないコツ】シリーズ
・アパート経営で失敗しないコツ #1(アパートとマンションの違い編)
・アパート経営で失敗しないコツ #2(物件編)
・アパート経営で失敗しないコツ #4(資金調達編)
・アパート経営で失敗しないコツ #5(家賃編)
・アパート経営で失敗しないコツ #6(管理編)
・アパート経営で失敗しないコツ #7(災害編)
・アパート経営で失敗しないコツ #8(売却・建て替え編)
・アパート経営で失敗しないコツ #9(総括編〜資産形成に向けて〜)
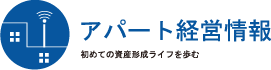 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


