
賃貸経営を行うに当たり、必ず経費としてかかってくるものは、各種の税金です。この税金をうまくコントロールできるかどうかが、賃貸経営の成功の鍵といっても過言ではありません。
ここで、賃貸経営に必須の税金の知識をおさらいしておきましょう。
賃貸経営にかかる費用と税金
収益物件にかかる経費を大まかに分けてみると、購入時にかかるものと所有時にかかるものがあります。また、物件を売却する際にかかる経費も考える必要があります。
購入時、所有時、売却時と3つに分け、それぞれのタイミングでかかる税金を見ていきましょう。
1. 購入時
●登録免許税
建物の新築・移転の際にかかる不動産移転登記、売買・相続・贈与で取得したときの保存登記、またローンを組むときの抵当権設定登記を行う際、必要となる税金です。通常、司法書士を通じて行います。
●印紙税
不動産の売買を行う際、契約書に印紙を貼ることにより納める税金が印紙税です。通常売り手と買い手の2通作成しますので、それぞれが負担します。また、金融機関から融資を受けて投資物件を購入する場合、金融機関と契約を締結する際にも、やはり印紙税がかかります。融資の金額により税金が変わってきます。
●不動産取得税
不動産を取得する際に、都道府県から課税されるのが不動産取得税です。本来は取得後数か月以内に申告納付することが決まりですが、制度が浸透していないこともあり、取得後半年から1年程度の間に物件のある自治体から納税通知が来ます。
2. 所有時
●固定資産税、都市計画税
物件を所有している間に支払わなくてはならないのが固定資産税と都市計画税で、課税標準に税率をかけて税額を出します。税率は通常、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%です。
3. 売却時
●不動産譲渡益にかかる所得税
個人で所有している物件の売却益が出た場合、譲渡益に対して税金がかかります。この税金は所得税ですが、他の所得と分離して計算されます。また、物件の保有期間(5年以下か5年超)によって短期譲渡所得か長期譲渡所得かに分類され、それぞれかかる税率が異なります。期間は物件を売却した年の1月1日時点で5年以下か超かを判断しますので注意が必要です。
節税方法の紹介
収益物件の取得時、所有時、売却時の3つにかかる税金を見てきましたが、それぞれの場面で上手に節税できることは可能でしょうか?
まず取得時にかかる税金は、課税標準が計算の基礎になるので、節税することが難しい税金です。ただ、印紙税など段階税率を採用している税金の場合、たまたま購入しようとしている物件が、より高い税率になるかどうかの境目の金額の場合、価格交渉で取得金額が下がれば税率も下げることが出来ます。
所有時にかかる所得税に関しては、減価償却を上手に使うことで税金を減らせます。所得税は、家賃収入などの収益から各種経費を差し引いた残りを元に課税標準を計算し、税率をかけて納税額を決定します。このため、家賃収入から経費になる減価償却やその他の経費をうまく差し引くことが節税につながります。
特に減価償却については、とても大切な概念です。キャッシュアウトなしに経費に落とせるものなので、これを上手に使いこなすことで節税になるケースが多いです。
売却時の譲渡益にかかる所得税は、5年超の長期所得では20.315%、5年以下の短期所得では39.63%と税率が著しく異なります。さらにその期間の計算は取得時から、売却時の日の年の1月1日までで、5年の判定を行います。よって、多額の売却益が出る物件を保有している場合、売却のタイミングがとても大切になってきます。
注意点
ここまで、収益物件にかかる税金と、その節税方法を書きました。もう少しアグレッシブに賃貸経営をする場合、法人化によって税金を抑えることが可能です。法人化の形式、維持費などの経費、家族の所得の状況などによって、節税効果が大きく左右されます。
また、法人化のポイントだけでなく、税法は年々改正されることが通常です。賃貸経営に精通した税理士などの専門家にしっかりと相談することにより、税務リスクをできるだけ小さくすることが可能となります。
税金をしっかりコントロールして、賃貸経営を成功に導きましょう。
【おすすめ記事】
・これで完璧! 不動産投資の節税対策
・サラリーマン大家の年収は?始めるなら頭金は?
・アパート経営っていくらかかるの? 知っておきたい経費と節税のコツ
・実は保険効果と年金効果がある!! 賃貸経営の本当の魅力とは
・サラリーマンや公務員こそアパート経営を始めるべき理由
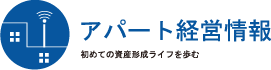 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


