
不動産投資は物件自体が高額なだけでなく、さまざまな費用が生じます。それらを的確に把握することが不動産投資を成功させるための第一歩です。
では、不動産投資にかかる費用は具体的にどのくらいなのでしょうか。
不動産投資にかかる初期費用の目安
不動産投資にかかる費用として、初期費用(イニシャルコスト)と保有費用(ランニングコスト)があります。まずは、初期費用からみていきましょう。
初期費用の主なものは以下のとおりです。
1.仲介手数料:物件価格×(3%+6万円)(400万円を超える金額の場合)
2.消費税:建物価格×8%(売手が業者の場合のみ)
3.不動産取得税:固定資産税評価額×3%×50%(宅地)
固定資産税評価額×3%(家屋)
4.登録免許税:固定資産税評価額×2%(土地・建物)
債権額×0.1%(抵当権)
5.司法書士報酬:1件数万円~(司法書士が任意に設定)
6.印紙税:不動産売買契約書(1通48万円以下)
金銭消費貸借契約書の印紙税(1通60万円以下)
仲介手数料は法定上限であり、引き下げ交渉も可能です。また不動産業者から直接買い付ければ手数料は発生しません。司法書士報酬も今は自由化されているため、交渉次第では安くなります。
不動産投資にかかる保有費用の目安
次に、保有費用について見てみましょう。不動産の保有費用には以下のものがあります。
1.管理委託費:賃料の5~10%(管理会社や委託業務の範囲により異なる)
2.少額修繕費:数十万円(破損した郵便ポストや電灯の修繕費など)
3.修繕積立金:賃料の3~5%(大規模修繕のための積立金)
4.火災保険料:年間数万円~数十万円
5.固定資産税:固定資産評価税額×1.4%(土地、家屋、償却資産)
6.都市計画税:固定資産評価税額×0.3%(土地、家屋)
7.借入金利息:1%台~5%程度
8.仲介手数料:賃料1ヵ月分×54%(上限)
9.広告宣伝費:賃料1ヵ月分程度(賃貸契約時に支払い)
業者に支払う費用は景気動向や交渉次第で変わります。とくに管理委託費、大規模修繕費(修繕積立金)、広告宣伝費は交渉余地が大きいでしょう。
税金は数年単位で変更されます。税率が変わるだけでなく、新たな税が制度化されたり逆に廃止されたりすることがあります。また不動産関連の税金は地方税が中心であるため、今後は物件所在地による差が大きくなるかもしれません。
不動産投資における利回りとは
不動産投資で使う利回りには、2種類あります。
・表面利回り
1年間の想定収入を物件価格で割ったものです(表面利回り=想定収入÷物件価格×100)。コストを反映していませんが手軽におおよその金額を計算できる便利さがあります。
・実質利回り
こちらは想定収入から管理委託費、固定資産税、都市計画税、借入金利息など支払額がほぼ決まっている予定費用を控除した粗利益を物件価格で割ったものです(実質利回り=粗利益<想定収入-経費>÷物件価格×100)。
プロの投資家はさらに精度を高めるため、空室率、貸倒率、賃料単価の改定、支払利息の変動、修繕積立金の増加など、より不確実性の高い要素も織り込みます。
利回りをみるときは、「高利回り=高リスク=低価格」となる場合が多いことに注意が必要です。賃料などの想定収入を一定の物件らと比較した場合、物件価格が低いほど高利回りとなります。これは空室、貸倒、賃料低下などの発生リスクが高ければ価格は下がるからです。
したがって、物件価格にはあらゆるリスク要因が反映されていることになります。その目利きが的確にできれば、割安な物件を探し出すことができます。
不動産投資の初心者が、リスク分析をして割安物件を見つけることは困難です。リスクに対する説明が不十分なまま高利回り物件を勧める業者には注意しましょう。良心的な業者は絶対にリスク説明を怠りません。
まずは、リスクの少ない低利回り物件の客観的な収支データを可能な限り入手することが大切です。その上で、実質利回りを計算し投資判断を下すといいでしょう。
【おすすめ記事】
・不動産投資のはじめ方ってなんだろう? 初心者に必要な基礎知識とは
・サラリーマン大家の年収は?始めるなら頭金は?
・セミナーに参加して、アパート経営を本気で始めてみませんか?
・実は保険効果と年金効果がある!! 賃貸経営の本当の魅力とは
・サラリーマンや公務員こそアパート経営を始めるべき理由
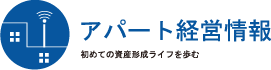 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


