
アパート経営の最大の収入源は家賃です。礼金、更新料、敷金も家賃と連動します。家賃の設定、値上げ・値下げ交渉の巧拙が、アパート経営で失敗しないための重要なカギとなります。
総コストと物件特性から家賃を決定
家賃設定において最初に検討すべきことは、総コストです。不動産取得税、登録免許税、仲介手数料、減価償却費、固定資産税・都市計画税、修繕費、水道光熱費、清掃費、警備費、管理委託費などアパートの取得・建設・運営に関するすべての費用を精緻に見積もることが大切です。
また空室リスクもコストの一部として認識する必要があります。住人の移動がある以上、必ず一定期間の空室が発生します。例えば学生向けアパートであれば、大学4年生と1年生が入れ替わる住戸の3月分の家賃はほぼゼロになると考えるべきです。このように、1部屋ごとの空室期間を可能な限り精緻に想定することが重要です。
総コストを賄える総家賃を試算した次の段階では、類似物件の家賃(相場)、マクロ経済情勢、立地特性、物件グレード、築年などを勘案して、家賃の上積み余地を検討します。
入居者の立場からみれば、それらの中で相場がもっとも重要な判断要素になります。このためコスト競争力が高ければ、柔軟な家賃戦略を採ることができます。相場よりも低い家賃にして空室を極力減らしたり、逆に強気の家賃を設定してグレード感を高めたりすることも可能です。
一方でコスト競争力が低い場合は、さまざまな工夫を要します。礼金、更新料、管理費、駐車場利用料、敷金などと合わせ総合的な収益確保策を検討することが大切です。
家賃を下げる一方で更新料や管理費を上げる、同じ間取りでも1階の中住戸の家賃を安くして2階の角住戸を高くする、家賃の一括前払(2年分など)と、それに伴う割引制度を導入するなど多様な手法が考えられます。退去時に大半を返還することが常識となった敷金をゼロにする(事後に修繕費を請求する)など大胆な策を打ち出せば、一段と注目を集めるでしょう。
いずれにせよ物件特性を踏まえ、多くの人にアピールする戦略を考える必要があります。とくに礼金・保証人・仲介手数料・更新料が不要のUR賃貸と競合する場合は、より魅力的な施策が求められます。
公正な家賃交渉が成功のカギ
家賃の値上げ・値下げの交渉方針を決めることも不可欠です。現代ではインターネットにより、同じアパートの空室や近隣物件の募集賃料を簡単に調べられます。こうした情報を踏まえ、契約更新時に賃料の値下げを求める入居者も大勢います。
そうした中で、アパート経営者には家賃の妥当性を説明するための準備が求められます。その結果として現行家賃が割高なことが判明すれば、自発的な値下げも検討すべきです。
アパート経営に失敗しないためには、適正収益を安定的かつ継続的に確保する(儲け過ぎない)という姿勢が大切です。公正な家賃とその設定ルールの透明性の確保は、入居者の信頼を得る上で重要な要素となります。
例えば、年(年度)初に部屋ごとの基準家賃を設定することや、契約更新時に当該年(年度)の基準家賃を提示することなどを定めて入居時に提示すれば、度重なる値下げ交渉にあう心配もありません。また、経済情勢の好転や不動産市況の上昇などから家賃を値上げしたいと思ったときにも、入居者に納得してもらいやすくなります。
アパートや不動産に関する知識を蓄え理論武装して契約や交渉に臨む入居者は、今後も増え続けると考えられます。家賃の設定・交渉に限らず、入居者と誠実に向き合うことがアパート経営に失敗しないための必須条件です。
かつての不動産賃貸市場では貸手(大家)が借手(入居者)より優位な立場にありましたが、今は対等な関係であることを認識する必要があります。
【失敗しないコツ】シリーズ
・アパート経営で失敗しないコツ #1(アパートとマンションの違い編)
・アパート経営で失敗しないコツ #2(物件編)
・アパート経営で失敗しないコツ #3(立地・環境編)
・アパート経営で失敗しないコツ #4(資金調達編)
・アパート経営で失敗しないコツ #6(管理編)
・アパート経営で失敗しないコツ #7(災害編)
・アパート経営で失敗しないコツ #8(売却・建て替え編)
・アパート経営で失敗しないコツ #9(総括編〜資産形成に向けて〜)
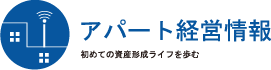 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


