
アパートの構造や性能は千差万別です。築50年を超える木造アパートから、頑丈な鉄筋コンクリート造の新築アパートまでさまざまあります。単純に躯体の頑強性に着眼すると新築鉄筋コンクリート造が望ましいですが、経営目線で見れば必ずしもそうとは言えません。
物件構造は木造、鉄筋コンクリート造など多様
アパートの躯体構造は以下の3種類に大別されます。
1. 木造
木造で一番多いのは在来工法(木造軸組み工法)です。相対的に安く建てられ零細な工務店でも施工できます。構造用合板を用いるツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)、同工法の構造材料の接着力を強化した木質パネル接着工法も木造に分類されます。
木造は耐震・耐火性能で劣るイメージがあります。しかし、柱の結合部分に金具を多用したり外壁に不燃材を使ったりするなど設計、材料、施工に手間とお金をかければ、大幅に性能を向上させることができます。
2. 鉄骨造(S造)
アパートで一番多い構造は軽量鉄骨造(プレハブ工法)です。工場で製造した部材を現場で組み立てるため、品質の安定度が高く耐久性にも優れています。一方で規格が標準化された工業製品であるため、寸法の自由度が低いとか増改築やリノベーションの制約が大きいなどの欠点があります。
アパートではあまり見受けられませんが、高層ビルなどと同じ工法の重量鉄骨造もあります。非常に頑強で間取りの自由度が高い点に特長があります。一方で建築コストの高さがマイナス要素となります。
3. 鉄筋コンクリート造(RC造)
鉄筋コンクリート造は、上下階や隣室間の遮音性や耐火性の点で優れています。外壁にタイルを張って高級感を演出することもできます。アパートの躯体としてはハイグレードになり高めの賃料設定も可能ですが、その分コストがかかります。
規定に則り適切に施工されれば非常に頑強な建物になるものの、 鉄筋・型枠・コンクリートの施工精度にバラツキが出やすいという欠点もあります。
建物寿命と構造材料の相関関係は不明?
財務省・PRE戦略検討会において、早稲田大学の小松幸夫教授は建物寿命と強い相関関係があるのは躯体の構造材料ではなく、使い方(メンテナンス)だと報告しています。
少し古いデータですが同教授の推計によれば、2005年時点の全国の平均寿命は木造共同住宅43.74年、鉄骨造共同住宅49.94年、鉄筋コンクリート造共同住宅45.17年となっています。最も寿命の長い鉄筋コンクリート造専用住宅でも56.74年にとどまっています。
同教授は、「傷みや陳腐化を補修・改修すれば新築と同じ」と述べています。構造材料の耐久性が劣ってもメンテナンスの手を抜かなければ、長く建物を使えるということです。建物寿命を決定する2大要素は構造材料とメンテナンスであり、アパート経営においては両者のバランスのとり方(コスト配分)が重要になります。
経営戦略に合致した構造物件の選択が重要
アパート構造の良否は一義的に決められるものではありません。自らの経営戦略に基づき選択すべきものです。増改築やリノベーションの自由度が高いことに着眼して古い木造物件を安く買い取りオリジナリティの高いデザインアパートへ改装することにより、高い利回りを実現している経営者もいます。
一方で単身者向けのコンパクトマンションが多い地域の場合は、設計や構造材料・設備に手間とお金をかけて高級感のあるアパートを造らなければ、入居者を集められないかもしれません。
また学生向けアパートであれば、耐久性と経済性に優れた軽量鉄骨造のアパートを建築して賃料の競争力を高める戦略が考えられます。
何れにせよ自らの嗜好、予算などの制約条件、地域特性などを検討して最も高い利回りを安定的に得られる可能性の高い構造を選択することが重要です。
【失敗しないコツ】シリーズ
・アパート経営で失敗しないコツ #1(アパートとマンションの違い編)
・アパート経営で失敗しないコツ #3(立地・環境編)
・アパート経営で失敗しないコツ #4(資金調達編)
・アパート経営で失敗しないコツ #5(家賃編)
・アパート経営で失敗しないコツ #6(管理編)
・アパート経営で失敗しないコツ #7(災害編)
・アパート経営で失敗しないコツ #8(売却・建て替え編)
・アパート経営で失敗しないコツ #9(総括編〜資産形成に向けて〜)
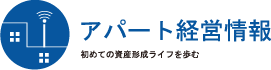 アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む
アパート経営情報 初めての資産形成ライフを歩む


